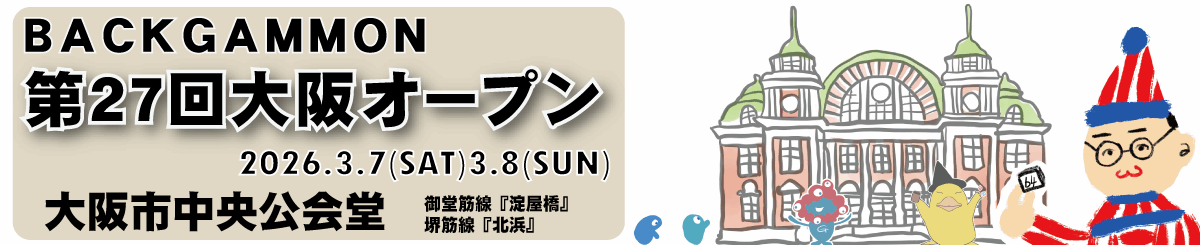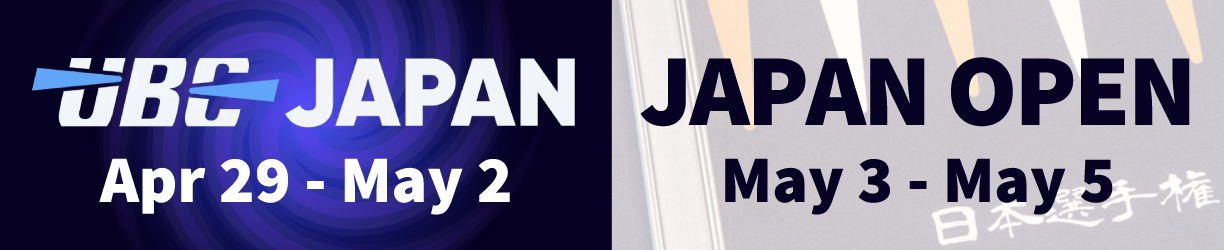寒さの中にも春の訪れを感じる2月半ば、東京都武蔵野市にある聖徳学園小学校にて、バックギャモンの特別授業をおこないました。今年は4年生の2クラス合同、合計68人の児童を対象に、100分のレッスンを実施しました。講堂を利用した広いスペースに一学年全員が一堂に会するようになったことで、スタッフが全体を見渡しながらフォローしやすくなりました。今回で4回目となる特別授業ですが、これまで以上に充実した内容となりました。
聖徳学園小学校では、1年生から4年生にかけて「知能訓練」と呼ばれる独自のカリキュラムを導入しています。バックギャモンをはじめとしたゲームやパズルを通じて、論理的思考力や集中力を育むことを狙いとしており、その歴史は実に50年以上に及びます。これは「10歳までの時期が最も学習能力を伸ばしやすい」という教育理論に基づいた取り組みですが、最近の研究でも、数字や確率を扱うボードゲームに親しむことが児童の数学的思考を養う上で有益であることが示されており、同校が長年バックギャモンを採用してきたのは非常に先進的な試みといえるでしょう。
当日の授業は次のように進めていきました。
① 導入(10分)
児童たちに興味を持ってもらえるよう、クイズなどのインタラクティブなやり取りを交えながら、場の一体感を高める導入をおこないました。

② ルールとマナー(30分)
すでに多くの児童がバックギャモンの基本ルールを理解していたため、ルールの再確認を中心に、ヒットとエンター、ブロック、ベアオフの手順などの重要なポイントをおさらいしました。また、今回はマナーをしっかり教えようという狙いがあったため、なぜマナーが大切なのか、そしてマナーを守るとどんな良いことがあるのか、具体例を交えて説明しました。

③ ブロックの練習(10分)
初期配置からブロックポイントを作る練習をおこないました。実際にやってみると、2枚のコマをうまく使えない子もいましたが、何度も繰り返し練習させることでスムーズに対局へ入れるよう準備を整えました。
④ 対局(50分)
児童たちがペアになり、望月プロを含めたスタッフ5名と順番に対戦しながら、児童同士の対局も同時進行でおこないました。10分の制限時間を設けてスタッフが勝敗を判定するという形式とし、児童全員がスタッフとの対局を体験できるようにしました。いくつかのペアはスタッフに勝利し、喜びを爆発させていました。


今年の特別授業では、インタラクティブなやり取りを増やすなど、新しい試みを積極的に取り入れました。子どもたちの楽しそうな表情や「もっと遊びたい!」という声は、教育ツールとしてのバックギャモンの大きな可能性を改めて示してくれました。バックギャモンには勝ち負けだけでなく、「戦略をどう立てるか」「最後まで粘り強く考える姿勢」などたくさんの学びが詰まっています。今回のような取り組みが将来、ワクワクしながら課題にチャレンジできる姿勢を育むきっかけになることを期待しています。
特別授業を支えてくださった聖徳学園小学校の先生方に改めて御礼申し上げます。児童のフォローアップ強化などさらなる改善点はあるものの、「教育的効果」と「ゲームとしての楽しさ」を両立させた取り組みとして、バックギャモン授業を今後もさらに発展させていきたいと考えております。バックギャモンが聖徳学園小学校においてより深く愛される存在となり、未来のチャンピオンがこの学び舎から誕生する日が来ることを、心から願っております。当協会としても、公教育の場でのバックギャモン普及に引き続き力を注ぎ、より良い授業づくりを目指していきたいと考えています。

日本バックギャモン協会では、教育機関・企業・各種団体を対象に、出張授業や講演会、講習会を開催しております。ご興味のある方は当協会(support@backgammon.or.jp)までお問い合わせください。
授業の様子についてはこちらの動画をご覧ください。